【ロジカルシンキングの基本】問題の核心を捉える「As-Is/To-Be」5ステップ活用術
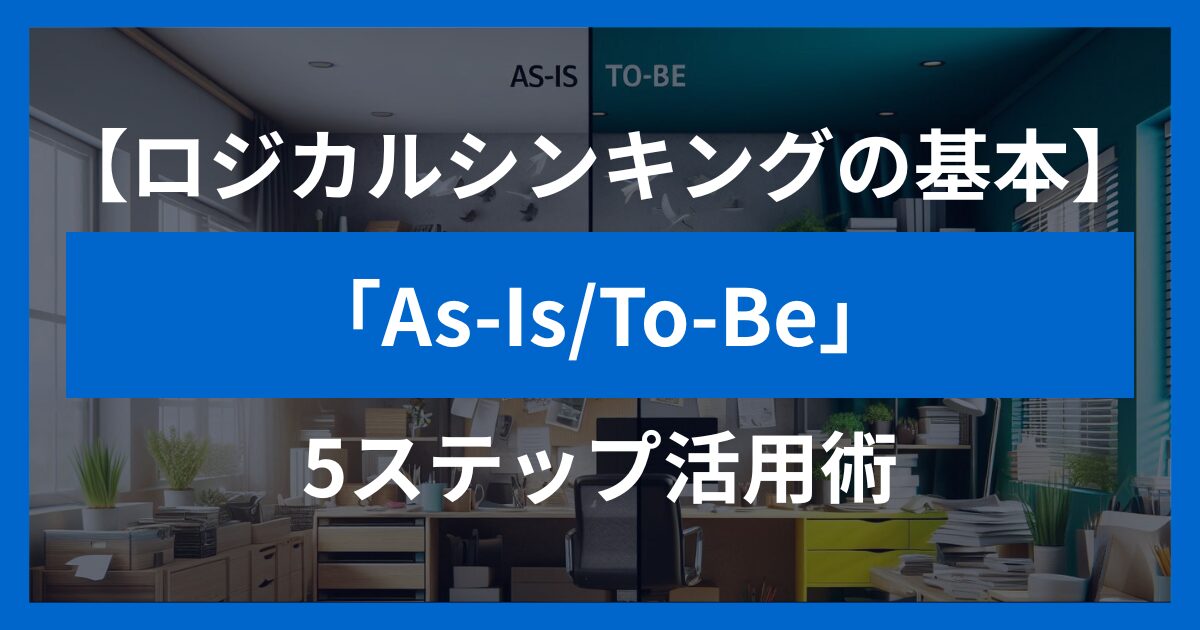
問題解決に取り組もうとする際、「解決策」や「行動」から考えてしまい、結局は「何となく効果が薄い」「議論が迷走する」といった経験はありませんか?
それは、そもそも「何を解決すべきか(課題)」が明確になっていないからです。
行き当たりばったりの解決策から脱却し、誰もが納得する論理的な課題解決を実現するために有効なのが、As-Is(現状)とTo-Be(理想)の考え方です。
この記事では、このシンプルなフレームワークを用いて、真の課題を特定し、具体的な行動に落とし込むまでの手順を、実践的な事例とともにご紹介します。
- 問題解決の議論で「何が言いたいのかわからない」と指摘される人
- プロジェクトのゴールや課題設定に自信が持てない人
- 具体的な行動にブレなく落とし込める課題設定方法を知りたい人
As-Is(アズイズ)とTo-Be(トゥービー)とは?
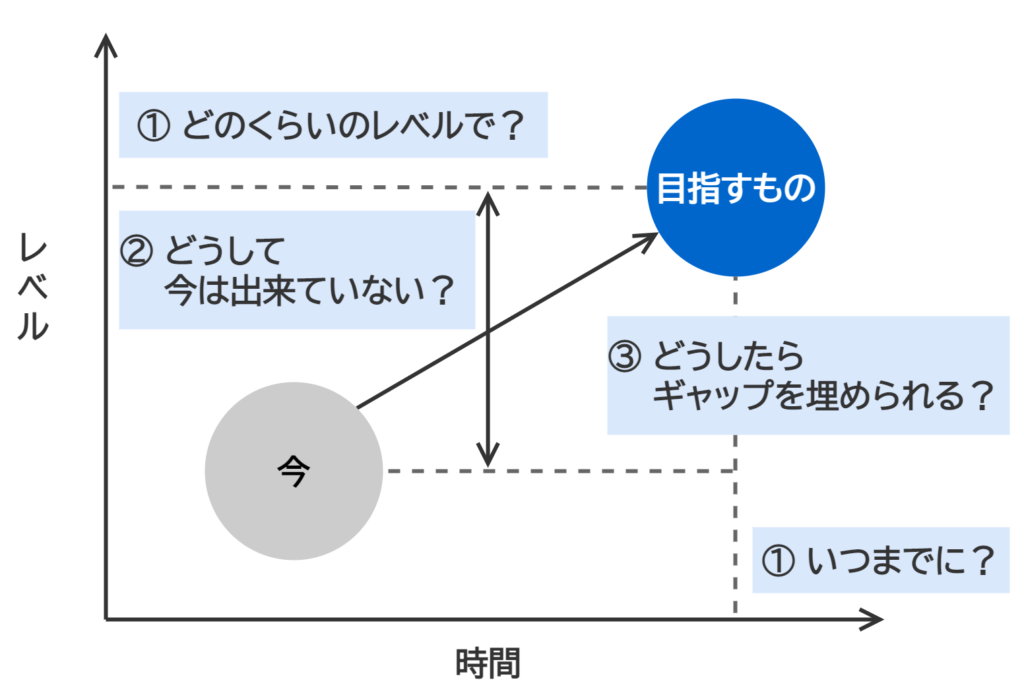
As-Is(アズイズ)は「現在の状態」、To-Be(トゥービー)は「理想の状態」を表す言葉です。
このフレームワークの目的は、現在の状態と理想の状態を正しく認識し、その間に存在する「ギャップ」を課題として抽出することにあります。
- 現状の問題を解決したい
- システム開発プロジェクトのゴールを定めたい
- チームや個人の目標を設定したい
このように、現状を変えたい、何かを実現したい、というあらゆる場面で活用できます。
As-Is/To-Beを活用する3つのメリット
As-Is , To-Beを使用するメリットは主に3つあります。
- 論理的に説明しやすい
- 複数人で議論しやすい
- 具体的な行動に落とし込みやすい
論理的に説明しやすい
①現在の状態→②理想の状態→③ギャップとなる課題→④行動
と順序立てて説明できるので、納得感のある説明をしやすいです。いきなり具体的な行動だけ説明されても「なんで?」となりますよね。
聞き手が納得しやすい、説得力のあるストーリーが自然と生まれます。
複数人で議論しやすい
下記のように、表にまとめて議論をすると複数人でも話しやすいです。
| テーマ | ①現在の状態 | ②理想の状態 | ③ギャップとなる課題 | ④行動 |
|---|---|---|---|---|
| テーマ1 | ||||
| テーマ2 |
- 今の状況はどうなっているのか?
- 自分たちはどうなりたいのか?
- その結果、課題はなにか?
このような問いから表を埋めていきます。
グループやチームとして、方向性が決まっていないと、後から修正する必要があります。しかし、この形式でディスカッションを行えば、皆の共通認識をあわせられるでしょう。
共通の表形式で「事実」と「目指すゴール」を可視化するため、認識のズレが生じにくく、建設的な議論を短時間で行えます。
具体的な行動に落とし込みやすい
ギャップとなる課題を解決するためにはどうしたらよいか?
という視点で考えられるため、具体的な行動に落とし込みやすいです。最初から課題を考え出すと、的はずれな行動になってしまうことがあります。
なぜなら、「現状」と「ありたい姿」を捉えられていないと、正しい認識ができないからです。
ギャップ」の解消に焦点を当てるため、抽象的な施策ではなく、的を射た具体的な行動に落とし込みやすくなります。
As-Is/To-Beの活用手順(具体例:残業削減)
ここでは、具体的な事例(残業時間の削減)を使って、As-Is/To-Beを実践する5つのステップをご紹介します。
1. (テーマ)何について考えるかを決める
まず、何について考えるかを決めます。
そもそも何が問題となっているのか、何を改善したいのかが分からないと話になりません。
例えば:
- 「残業時間を減らしたい」
- 「新商品をPRして売上を上げたい」
などでOKです。どんな要求や目的があるかな?の視点で考えてみましょう。
今回の例では、「残業時間を削減したい」ことをテーマに設定しました。
2. (As-Is) 事実ベースで現在の状況を整理する
As-Isでは、主観ではなく、定量的な事実ベースで現状を正確に把握することが重要です。
- 主観:最近忙しい
- 事実:直近3ヶ月の月平均の残業時間が40時間を超えている
事実ベースのほうが具体的で分かりやすいですね。
- 直近3ヶ月の月平均の残業時間が40時間を超えている
- 同じ職場の同僚と比較すると、20時間以上多い
- 主に提案書を作成することに時間を割いている
難しく考えず、思いついたものをどんどんリストアップしましょう。不要な情報は後で削れば問題ありません。
3. (To-Be) 現在の状況に対応する理想の状態を書き出す
As-Isで書き出した項目から、「理想の状態」を書いていきましょう。
- As-Is:直近三ヶ月の月平均の残業時間が40時間を超えている
- To-Be:直近三ヶ月の月平均の残業時間を10時間以内に抑えられている
実現可能性を深く考えずに、理想の状態を追求しましょう。最初から出来るか出来ないかを考えてしまうと、思考が狭くなってしまいます。
4. (課題)ギャップから課題をつかむ
As-IsとTo-Beの間に存在するギャップ(差)は何か?そして、「なぜそのギャップが生まれているのか?」という真の原因(ボトルネック) を特定します。
多くの人が見落とす最重要ステップです。
| As-Is (40h) | ギャップ | To-Be (10h) |
|---|---|---|
| ギャップ: 残業時間が30時間多い | 原因分析: なぜ30時間も多いのか? → 真の原因: 報告書の作成フローが属人化し、毎月ムダな手戻りが発生しているため。 | 理想の状態 |
この「真の原因」こそが取り組むべき課題となります。
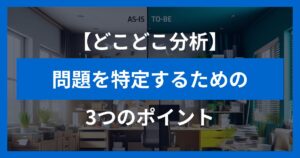
5. (行動)具体的な行動に落とし込む
特定した真の原因を解消するために、「いつ」「何を」「誰が」やるのか、具体的な行動に落とし込みます。
- 課題(真の原因)
-
報告書の作成フローが属人化しており、時間がかかっている。
- 具体的な行動
-
1. 報告書のテンプレートを作成し、全社に展開する。
2. 作成にかかっている時間の内訳を1週間計測し、ムダを特定する。
3. 同僚の報告書の作り方をヒアリングし、ベストプラクティスを共有する。
大事なのは、行動することです。真の原因に基づいた行動であれば、結果がついてくる可能性が高まります。
まとめ
As-IsとTo-Beは、シンプルながらも問題解決、目標設定、プロジェクトの方向付けなど、幅広い場面で活用できる強力なフレームワークです。
- 「現状」と「理想」を明確にすることで、取り組むべき課題を論理的に特定する。
- その真の原因に焦点を当てた行動をとることで、ブレのない解決策を実行する。
ぜひこの5ステップを習慣化し、職場でもプライベートでも理想の姿を実現できるよう活用してみてください。

コメント